Sponsored Link
中和滴定のグラフ
前回の直接滴定と逆滴定、対応量の計算では基本的な計算についてみました。今回からは滴定の各論です。まず中和滴定です。
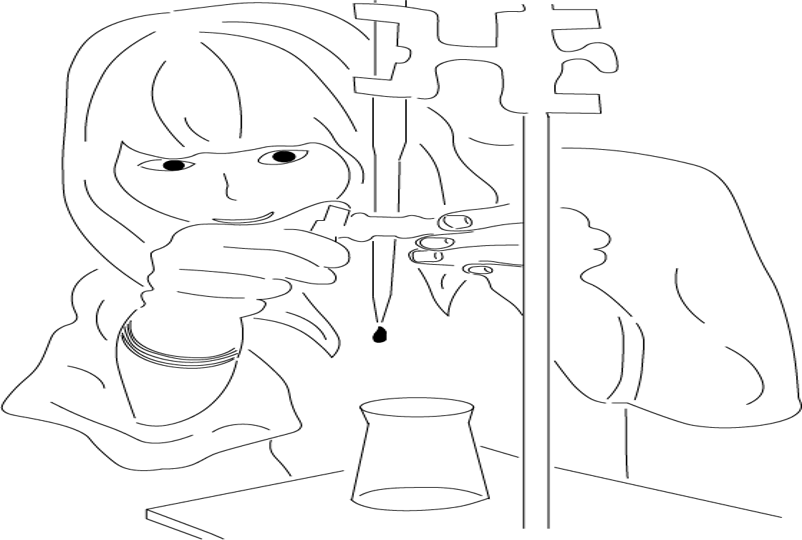
中和滴定
中和滴定は酸性医薬品や塩基性医薬品を中和反応を利用して滴定する方法です。それぞれの医薬品では以下のようなものが標準液として使われます。
- 酸性医薬品;水酸化ナトリウムや水酸化カリウムなどが標準液として使われる
- 塩基性医薬品;塩酸や硫酸などが標準液として使われる
なお、中和滴定や次回の非水滴定では指示電極にはガラス電極が使われます。ガラス→クリスタル→ヒスイ→中和(酸塩基つながり)とイメージすると覚えやすいかもしれません。
Sponsored Link
Sponsored Link
中和滴定の指示薬
中和滴定の指示薬はpHの変化により指示薬の構造が変わることによって色の変化が起こります。いくつか種類がありますが、代表的なものには以下のものがあります。
- メチルオレンジ;赤色〜黄色(pH3.1〜4.4)
- メチルレッド;赤色〜黄色(pH4.2〜6.2)
- フェノールフタレイン(pH8.3〜10.0)
これらの指示薬を使って中和滴定を行うと滴定曲線がえられ、酸と塩基の組み合わせによって曲線が変わってきます。当量点近くにおけるpHの急激な変化をpH飛躍(pHジャンプ、pHjump)と呼びますが、その位置が異なります。

- 強酸と強塩基;pHジャンプは酸性側から塩基性側であるため、ほとんどの指示薬が使える
- 弱酸と強塩基;pHジャンプは塩基性側であるため、フェノールフタレインなどの指示薬を使う
- 強酸と弱塩基;pHジャンプは酸性側であるため、メチルオレンジやメチルレッドなどの指示薬を使う
- 弱酸と弱塩基;明確なpHジャンプは見られない
ではグラフの問題を見てみましょう。
例題
以下の4種類の中和滴定を行った
- 0.1mol/L塩酸10mLを0.1mol/L水酸化ナトリウム水溶液で滴定する
- 0.01mol/L塩酸10mLを0.01mol/L水酸化ナトリウム水溶液で滴定する
- 0.1mol/L酢酸10mLを0.1mol/L水酸化ナトリウム水溶液で滴定する
- 0.1mol/Lアンモニア水10mLを0.1mol/L塩酸で滴定する
この時のそれぞれのグラフは次のうちどれになるか答えよ。

0.1mol/L塩酸10mLを0.1mol/L水酸化ナトリウム水溶液で滴定する
強酸と強塩基の組み合わせです。次の選択肢と比べて強酸も強塩基も高濃度であるため、pHジャンプは大きくなります。そのためBのグラフが正解です。
0.01mol/L塩酸10mLを0.01mol/L水酸化ナトリウム水溶液で滴定する
強酸と強塩基の組み合わせです。前問の解説通り、こちらの方が強酸も強塩基も低濃度であるため、pHジャンプは小さくなります。そのためAのグラフが正解です。
0.1mol/L酢酸10mLを0.1mol/L水酸化ナトリウム水溶液で滴定する
弱酸と強塩基の組み合わせです。そのためpHジャンプは塩基性側に見られるので、Dのグラフが正解です。
0.1mol/Lアンモニア水10mLを0.1mol/L塩酸で滴定する
弱塩基と強酸の組み合わせです。そのためpHジャンプは酸性側に見られるので、Cのグラフが正解です。
まとめ
- 中和滴定ではガラス電極が使われる
- 中和滴定の指示薬は、酸塩基の組み合わせによって使い分けられる
中和滴定のグラフ 関連ページ
- 双極子とファンデルワールス力
- 電荷の偏りによって双極子ができて、相互作用が発生します。ファンデルワールス力の引力は分子間距離の6乗に反比例します。
- 水素結合と疎水性相互作用
- 水素結合は沸点や密度、溶解性などに影響を与えて、DNAの二重らせんなどに関わっています。疎水性相互作用はミセル形成などに関わっています。
- 電磁波と吸光度
- 電磁波のエネルギーは振動数が大きい、もしくは波長が小さいほどエネルギーが高くなります。吸光度は試料を通過する光路長lと試料中の化合物の濃度cに比例し、これをLambert-Beerの法則と言います。
- 比吸光度、モル吸光係数の計算
- 比吸光度、モル吸光係数の計算はLambert-Beerの法則などを使って計算を行います。計算問題が解けるようになる必要があります。
- 紫外可視吸光度測定法の原理
- 紫外可視吸光度測定法はπ結合が紫外線や可視線などの光を吸収して遷移するのを原理として利用され、共役不飽和結合系の存在の確認に使われます。
- 紫外可視吸収スペクトル、発色団と助色団
- 紫外可視吸収スペクトルにおいて、π電子を持つものを発色団、ローンペアを持つものを助色団と言います。また長波長側への移動を深色効果(レッドシフト)、短波長側への移動を浅色効果(ブルーシフト)と言います。
- 蛍光光度法のまとめ
- 蛍光光度法の試料部には、四面透明の無蛍光の石英製セルを用います。ガラス製では紫外部の光を吸収するから不適です。また蛍光光度法の検出部は励起光に対して90°に置きます。
- 赤外吸収スペクトル(IRスペクトル)の読み方
- 赤外吸収スペクトル(IRスペクトル)では、水酸基(OH)は3600〜3200あたりの幅広い吸収、カルボニル基(C=O)は1700あたりの吸収が見られます。
- 旋光度、旋光分散、円偏光二色性
- 旋光分散は、波長を変化させて旋光度を測定します。これによって得られた曲線でコットン効果が起こることがありますが、それは円偏光二色性などが関わります。
- 核磁気共鳴スペクトル(NMR)の原理
- 核磁気共鳴スペクトル(NMR)の原理は、ラジオ波を受けて核磁気共鳴を起こすことによります。さらに緩和を起こし、緩和を利用したものがMRIです。
- 1HNMRスペクトルの読み方、知識編
- 1HNMRスペクトルを読むには、シグナル面積強度、カップリング(スピンースピン結合)、重水素交換法などが重要になってきます。
- 1HNMRスペクトル、例題編
- 1HNMRスペクトルの問題は、それぞれの化学シフトをパズルのようにパーツごとに考えて組み合わせていくことで解くことができます。
- 光の進路と屈折率
- 光の屈折率は、入射角によらず一定の値をとり、これをスネルの法則と言います。日本薬局方では、屈折率は空気に対する値で示し、温度は20℃、ナトリウムスペクトルのD線を使って測定されます。
- 放射壊変(α壊変、β−壊変、β+壊変、軌道電子捕獲、γ放射)
- 放射壊変にはα壊変、β−壊変、β+壊変、軌道電子捕獲、γ放射などがあります。親核種や娘核種がどのようになり、どのような放射線を出すかをおさえましょう。
- α線、β−線、β+線、γ線、X線の物質相互作用や透過力
- 放射線には、α線、β−線、β+線、γ線、X線などがあり、物質相互作用や透過力が異なります。またスペクトルも線スペクトルなのか、連続スペクトルなのかもおさえましょう。
- 放射線の単位と、放射平衡
- 放射線に関わる単位には、Bq(ベクレル)、Gy(グレイ)、Sv(シーベルト)などがあります。放射平衡には、過渡平衡と永続平衡があり、親核種と娘核種の半減期によって決まります。
- 放射線の測定方法と身体への影響
- 放射線の測定方法には、ガイガーミュラー計数管、液体シンチレーションカウンタ、NaI(TI)シンチレーションカウンタなどがあります。放射線の被曝の障害には確定的影響と確率的影響などがあります。
- 気体分子運動論、並進運動、回転運動、振動運動
- 気体分子の運動エネルギーは、並進運動エネルギーと回転運動エネルギーと振動運動エネルギーの和で表されます。振動や回転は不連続な値をとりますが、並進は連続しているとみなされます
- 熱力学1、系と状態関数のまとめ
- 熱はエネルギーを持っていて、仕事をすることができます。開いた系と反対になるのは孤立系です。示量性状態関数は足し算ができますが、示強性状態関数は足し算ができません。
- 熱力学2、熱力学第一法則と熱容量
- 運動エネルギーと位置エネルギーの総和を内部エネルギーと言い、孤立系の内部エネルギーが一定であることを熱力学第一法則と言います。定容熱容量は定圧熱容量より小さくなります。
- 熱力学3、エンタルピーとは?ヘスの法則の計算
- エンタルピーとは物質が持つエネルギーの総量で、内部エネルギーと圧力や体積のエネルギーの和で表されます。エンタルピーに関連したものにヘスの法則があり計算できるようになりましょう。
- 熱力学4、エントロピーとは?熱力学第二法則との関係
- エントロピーは乱雑さの指標で、物事の不可逆性についての指標とも言えます。エントロピーに関連したものに熱力学第二法則があります。
- 熱力学5、ギブズ(Gibbs)エネルギーとは?
- ギブズ(Gibbs)エネルギーの変化量は、エンタルピーとエントロピーの変化により決まります。ΔGがマイナスになるのが自発的な反応であり、ΔG=0の時は平衡状態を意味します。
- 熱力学6、van’t Hoff式(ファントホッフ式)のグラフ
- ギブズ(Gibbs)エネルギーの圧力と温度による変化グラフでは、圧力一定の時は傾きが−S、温度一定の時は傾きがVとなります。van’t Hoff式(ファントホッフ式)のグラフではΔH゜、ΔS゜を求めることができます。
- 状態図と自由度
- 状態図の三重点では、固相、液相、気相の3つの状態が存在します。自由度(F)=成分の数(C)−相の数(P)+2で表されます。
- 2成分の気液平衡の状態図
- 2成分の気液平衡の状態図では、気相中と液相中の成分の変化をしっかりと見極めることが大事です。また蒸留を繰り返していくことで、2つの成分を分留することができます。
- 共沸点を持つ場合の状態図
- 共沸点をもつ状態図の場合では、左と右にわけて考えれば前回と同じ考え方で対応できます。また上にとんがったグラフでは発熱反応、下にとんがったグラフでは吸熱反応です。
- 液液平衡の状態図
- 液液平衡の状態図において、曲線の内側だと2相、曲線の外側だと1相になります。液液平衡の状態図において、高温で1相になる上部臨界溶解温度を持つ系では、一般的に混合熱は吸熱となります。
- 固液平衡の状態図
- 固液平衡の状態図においては、気液平衡と同じように考えれば問題ありません。固液平衡の状態図においては、共融点より下まで冷却すると固相のみとなります。
- 束一的性質とは?
- 実在する溶質粒子の数に依存して、溶質の種類が何であるかには依存しない性質を束一的性質と言います。沸点上昇、凝固点降下では解離度が関わります。
- 反応速度、概論
- 反応速度では、0次反応は、一定速度で分解していく反応です。1次反応は、一定割合で分解していく反応、2次反応は、半減期は初濃度に反比例します。
- 0次反応の式とグラフ、例題編
- 0次反応の式では縦軸の切片はC0、傾きは−kの直線的なグラフとなります。また0次反応の式では、2半減期以降だと濃度は0となります。
- 1次反応の式とグラフ、例題編
- 1次反応の式とグラフはlnの時は切片はlnC0、傾きは−kの直線的となります。logの時は縦軸の切片はlogC0、傾きは−k/2.303となるので注意が必要です。
- 2次反応の式とグラフ、例題編
- 2次反応は縦軸の切片は1/C0、傾きはkの直線的なグラフとなります。。0次反応や1次反応と異なり、傾きがプラスであるのがグラフとしては特徴的です。
- 擬0次反応の式とグラフ、例題編
- 擬0次反応とは懸濁剤(サスペンション)などにおいて、溶液中の分解速度が、固体の溶解速度よりも遅いために、本当は1次反応なのに、0次反応のマネをするような式やグラフとなります。
- 擬1次反応、特殊酸触媒と特殊塩基触媒
- 擬1次反応には、エステルの特殊酸触媒と特殊塩基触媒の反応などがあります。特殊酸触媒と特殊塩基触媒の影響を受ける医薬品では、kH[H+]=kOH[−OH]の時が最も安定となります。
- 活性化エネルギーと反応エンタルピー
- 活性化エネルギーが大きいほど反応が進みにくく、小さいほど反応が進みやすいです。触媒は活性化エネルギーに影響を与えて、反応エンタルピーには影響を与えないということができます。
- Arrhenius式(アレニウス式)とグラフ
- Arrhenius式(アレニウス式)は、反応速度と温度の関係を表した式です。アレニウスプロットではそのグラフから薬の安定性などがわかります。
- 酸と塩基の基本
- 酸と塩基のには、Arrhenius(アレニウス)の定義、Lewis(ルイス)の定義、BronstedーLowry(ブレンステッド・ローリー)の定義などがあります。弱酸においてはKa=[A−]・[H+]/[HA]が成り立ち、Kaを酸解離定数と言います。
- 弱酸のpHの計算
- pH=−log[H+]で表されます。強酸の場合は、全て解離するためpHの計算はやりやすいですが、弱酸の場合は[H+]=√(Ka・C)で計算する必要があります。
- Henderson-Hasselbalch(ヘンダーソンーハッセルバルヒ)の式と計算
- あるpHのおける弱電解質の分子形やイオン形の割合を求めるのがHenderson-Hasselbalch(ヘンダーソンーハッセルバルヒ)の式です。Henderson-Hasselbalch(ヘンダーソンーハッセルバルヒ)の式を使って計算できるようになりましょう。
- 真度と精度の違い
- 真度は真の値からのかたよりの程度です。精度は均質な検体から採取した複数の試料を繰り返し分析して得られる一連の測定値が互いに一致する程度です。真度と精度の違いを間違えないようにしましょう。
- 容量分析法、標定と滴定
- 容量分析法には中和滴定、非水滴定、キレート滴定、沈殿滴定、酸化還元滴定などがあり標準液、標準試薬、指示薬が決まっています。
- 直接滴定と逆滴定、対応量の計算
- 直接滴定と逆滴定によって、対応量を計算します。対応量とは用いた標準液1mLに対応する資料の量(mg)のことで、おちついて計算できるようにしましょう。
- 非水滴定、キレート滴定
- 非水滴定は、きわめて弱い酸や塩基を滴定します。キレート滴定はエチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム(EDTAナトリウム)と金属イオンは1:1で反応します。
- 沈殿滴定、Fajans法(ファヤンス法)、Volhard法(フォルハルト法)
- 沈殿滴定は銀を利用して、Fajans法(ファヤンス法)やVolhard法(フォルハルト法)などがあります。沈殿滴定では銀イオンがハロゲン化物(フッ素以外)、シアン化物イオン(CN-)、チオシアン酸イオン(SCN-)などと反応します。
- 酸化還元滴定、ジアゾ滴定
- 酸化還元滴定では、デンプン試薬が指示薬として使われるが、過マンガン酸カリウムについてはそれ自体が指示薬として働きます。ジアゾ滴定は酸化還元滴定の1つです。
- クロマトグラフィーの原理と種類
- クロマトグラフィーの原理は、試料の固定相への親和性の違いによって分離します。クロマトグラフィーの移動相固定相による分類では、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどがあります。
- 保持時間(tR)、分離度(Rs)、分離係数(α)、シンメトリー係数(S)、カラム効率
- クロマトグラムの指標には、保持時間(tR)、分離度(Rs)、分離係数(α)、シンメトリー係数(S)、カラム効率などがあります。分離度(Rs)と分離係数(α)の違いは、ピーク幅があるかどうかです。
- クロマトグラフィーの定性と定量
- クロマトグラフィーの定性には保持時間が使われます。クロマトグラフィーの定量は、ピーク高さやピーク面積を用いる。方法には内標準法、絶対検量線法、標準添加法などがあります。
- ガスクロマトグラフィーと検出器
- ガスクロマトグラフィーの検出器には、熱伝導度検出器、水素炎イオン化検出器、電子捕獲検出器、炎光光度検出器、アルカリ熱イオン化検出器などがあります。
- 液体クロマトグラフィーと種類
- 液体クロマトグラフィーの種類は固定相により吸着クロマトグラフィー、分配クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、ゲルクロマトグラフィーなどにわけられる。
- 溶媒抽出法、固相抽出法、除タンパク法
- 溶媒抽出法は、水と有機溶媒の中に試料を入れることで、目的物質を片方の層に移すことで、邪魔者と分離する方法です。固定抽出法は固相を用いて、目的物と邪魔者を分離する方法です。
- イムノアッセイとは?
- 標識するイムノアッセイには、ラジオイムノアッセイ(RIA)、エンザイムイムノアッセイ(EIA)、蛍光イムノアッセイ(FIA)、発光イムノアッセイ(LIA)などがあります。
- 電気泳動法の原理
- 電気泳動法の原理は、電荷のある物質を電極の間に入れて電圧をかけることで分離を行います。イオンの電荷により分離する電気泳動法には、等電点電気泳動法、等速電気泳動法などがあります。
- SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動法(SDS-PAGE)とは
- SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動法(SDS-PAGE)では、還元剤でバラしたタンパク質に対して、陰イオン界面活性剤を加えて負に帯電させて電気泳動することで、小さいタンパク質ほど陽極へ速く移動します。
- キャピラリー電気泳動法とは
- キャピラリー電気泳動法は、キャピラリーを用いることで電気二重層がつくられ、陰極側に強い流れが起こります。キャピラリーゾーン電気泳動法、ミセル動電クロマトグラフィーなどの種類があります。
- X線検査(レントゲン)とCT検査
- X線検査(レントゲン)とCT検査はX線の吸収率を利用して画像を撮影します。X線造影撮影法は、硫酸バリウムやヨード造影剤などの造影剤を用いて吸収率を変えて撮影をしやすくしています。
- MRIの原理と中止するべき薬
- MRIで一時中止すべき薬にはニコチネルTTS(ニコチン)、ニトロダームTTS(ニトログリセリン)、ノルスパンテープ(ブプレノルフィン)、ニュープロパッチ(ロチゴチン)などがあります。
- 超音波検査(エコー)の原理
- 超音波検査(エコー)は超音波の反射波を利用して画像撮影する検査です。超音波検査(エコー)は絶食状態で行うことが多いため糖尿病治療薬などは中止になる可能性があります。
- 質量分析法のイオン化法
- 質量分析法においてイオン化するには、電子イオン化(EI)法、化学イオン化(CI)法、高速原子衝撃(FAB)法、エレクトロンスプレーイオン化(ESI)法、マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)法などがあります。
- 質量分析法の質量分析計と質量スペクトル
- 質量分析法の質量分析計には磁場型、飛行時間型、四重極型などがあります。質量スペクトルでは臭素(Br)や塩素(Cl)、そして窒素を含む場合のルールを知っておく必要があります。
- 質量スペクトルの読み方、例題編
- 質量スペクトルの読み方や解き方について解説しています。特に臭素や塩素を含む場合はスペクトルが特徴的なものとなるので見逃さないようにしましょう。
